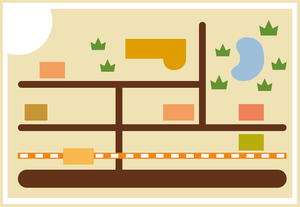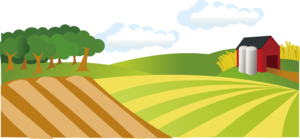土地改良区とは?農地転用時の意見書の取得や申請の手続きについても紹介

農地が土地改良区に加入しているとき、住宅用地や駐車場などに転用するには「地区除外」の手続きが必要だということをご存じでしょうか。
この手続きを見落とすと、農地転用の許可申請が進まず、その後の計画全体が遅れてしまう可能性があります。
土地改良区とは何か、除外手続きはどのように進めるのか、これら基本的なことをここでチェックしていきましょう。
土地改良区とは?
土地改良区は、「農業を行う地域で用水路やため池、排水施設などを整備・管理するために設立される公的な法人」のことです。
土地改良法という法律に基づいて組織され、地域の農地環境や農業用水を守る役割を担っています。
具体的には、区画整理や用排水路の新設・維持管理、農道の整備といった活動を実施します。
こうした事業には公的資金が投入されることも多く、圃場の生産性向上や農業経営の効率化を目的としています。
その地域内で農地を持つ方は、基本的には自動で会員(組合員)として加入することになります。
費用は公的資金や組合員の負担(賦課金)で賄われ、これにより水路の修繕や施設管理が行われます。
地元の田んぼや畑の水路が適切に管理されているのは、土地改良区の存在があるからこそといえるでしょう。
農地転用には土地改良区の意見書が必要
農地を住宅や駐車場など農業以外の用途に変える(これを「農地転用」という)とき、当該土地が土地改良区の管理区域内にあるのなら、原則として土地改良区から「意見書」または「同意書」と呼ばれる文書を取得しなくてはなりません。
なぜ意見書等が必要かというと、その土地が水路や用排水施設の管理・利用に影響を及ぼす可能性を持っているためです。
農地を自由に転用できてしまうと、水の流れや施設の維持管理に支障が出るかもしれません。
こうした問題が起こらないよう、土地改良区は転用による影響がないかをチェックする立場にあるのです。
土地改良区が同意してくれない、農業委員会や都道府県による転用許可が下りない、といったことが起こると手続きが大幅に遅れることもあります。
また、転用地が農業用水路や施設と一体になっているケースだと、その移管や撤去に関しての調整・交渉が必要になることもあるでしょう。
土地改良区から除外してもらうための手続き
農地転用、土地改良区からの除外を行うには、申請が必要です。
その前提として対象となる土地が土地改良区に該当するのかどうかをチェックすることも大事です。
また、手続きに関しては地区除外決済金の存在についても知っておいた方が良いでしょう。
土地改良区に該当するか確認
転用予定の農地が土地改良区に入っているかどうかは、市町村の農業委員会事務局に問い合わせることで確認できます。
農業委員会に聞けば、どの土地改良区が関係するのか、具体的な連絡先も教えてもらえるでしょう。
地区除外申請を行う
土地改良区に該当することがわかれば、地区除外申請の手続きに着手します。
そこでまず土地改良区の事務局に連絡し、転用予定であることを伝えて相談しましょう。
その後は「地区除外申請書」や「意見書交付願」、「誓約書」など土地改良区指定の書式で作成した書面を提出します。
添付資料として位置図や公図なども必要になります。
地区除外決済金の納付
申請書を提出すると「決済金納入通知」が届きますので、この決済金(「地区除外決済金」「清算金」などと呼ばれることもある)を指定の口座へ納付して、「意見書」を発行してもらいましょう。
※地区除外決済金とは、土地改良区から除外される際に支払う費用のこと。過去の投資や将来の維持管理費用を精算する趣旨で支払いが求められる。なお、金額は面積やエリアによっても異なる。
発行された意見書を農地転用許可申請書と一緒に農業委員会へ提出することで、転用手続きが進められます。
手続きは専門家に依頼するのがおすすめ
土地改良区の地区除外申請や農地転用許可申請は、提出書類や段取りが土地改良区や自治体ごとに異なり、提出先・時期・納付方法など確認事項も多く大変な作業となります。
申請ミスや順序ミスがあると許可が遅れることもあるため、事前の確認も重ねたほうが安全です。
特に、初めて農地転用に取り組む方や複数の地権者が関係するケース、仕事で多忙な方などは、行政書士に依頼することをおすすめします。
行政書士には書類作成・提出代行・関係機関との調整などを任せられるため、スムーズかつ着実に手続きを進めていけます。
農地転用や土地改良区の手続きでお困りなら、ぜひ専門家へご相談ください。